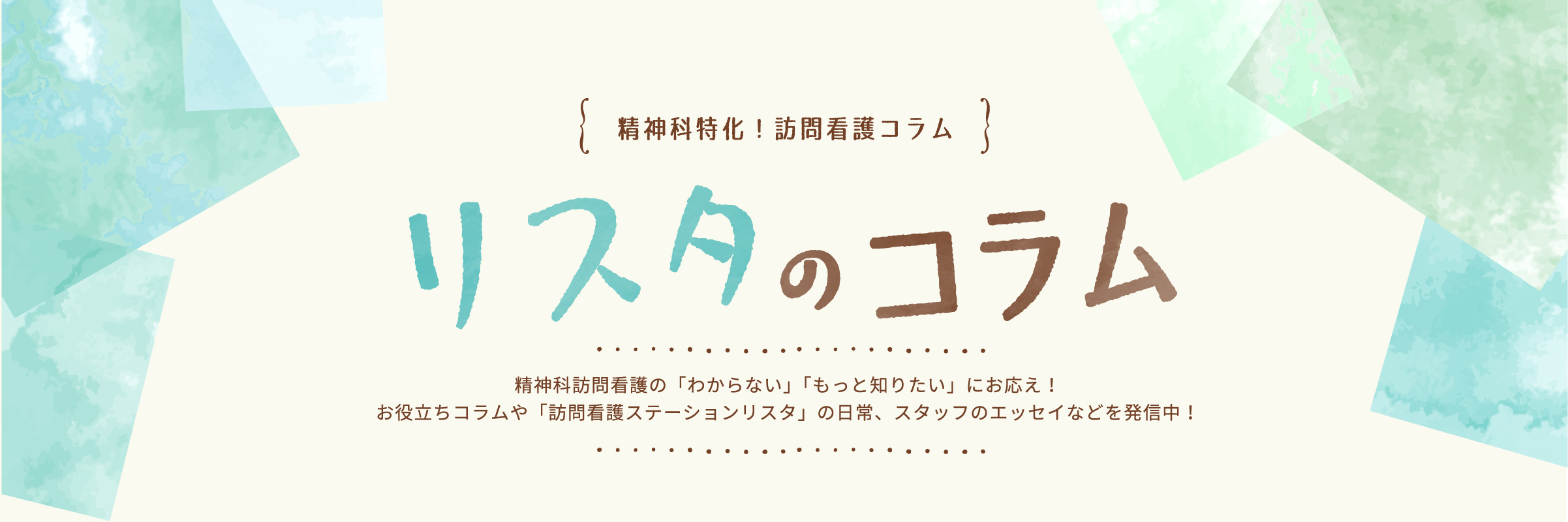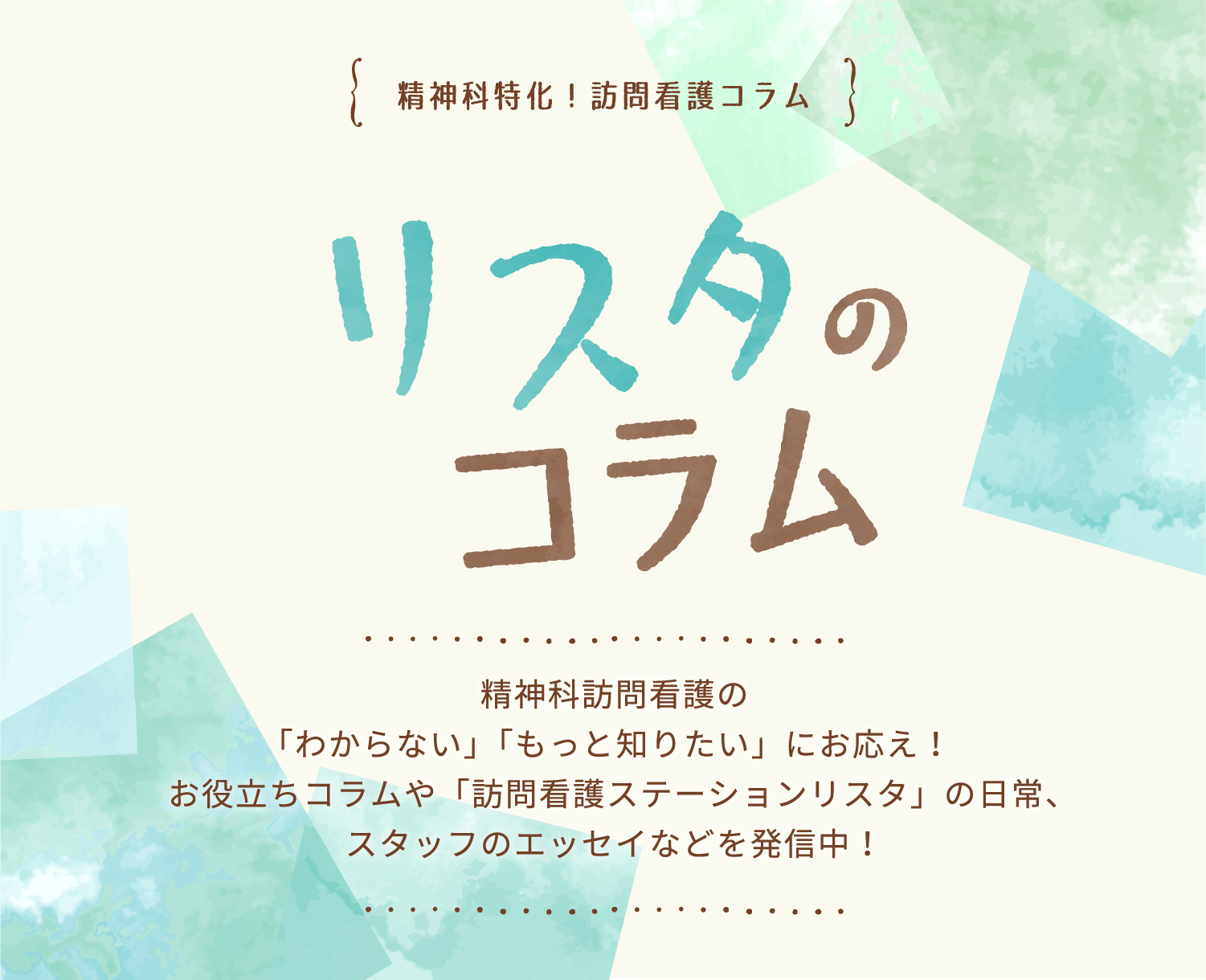「てんかん」に対する看護のポイントや基礎知識をわかりやすく解説
2025.03.21
てんかんは自閉スペクトラム症や高次脳機能障害、精神症状が合併することも多く、さまざまな診療科でてんかんを持つ患者さまに関わります。
しかし、実際にてんかん発作の対応や生活指導をしたことがある方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、てんかんの基本知識と看護のポイントを解説します。
てんかんについて学びを深めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
てんかんとは
てんかんとは、脳の異常な興奮性の神経活動によって発作を繰り返す状態です。
運動神経や高次脳機能などの神経系で、異常な活動が起こり、以下のような症状が見られます。
・体の一部が固くなる
・体の一部がピクつく
・手足のしびれ
・動悸
・眼球偏視
・けいれん
・意識消失 など
検査では、画像検査(CT、MRI)や脳波検査、血液検査、心理検査などが実施され、多角的視点で評価されます。
てんかんと診断されると長期間の治療が必要なケースもあるため、診断は慎重に行われます。
具体的な治療としては、薬物療法(抗てんかん薬の服用)が一般的です。状態によっては、外科的療法、迷走神経刺激術などが選択される場合もあります。
参照:国立精神・神経医療研究センター/てんかん
てんかんを持つ患者さまへの看護のポイント
次は、てんかんを持つ患者さまを看護するときのポイントを解説します。
てんかん発作を起こさないための環境調整
てんかんの治療は、てんかんの発作を防ぐことが目標です。
てんかん発作はストレスや不規則な生活、体温上昇などさまざまな要因で引き起こされます。
そのため、看護師は次のような指導をして、患者さまがてんかん発作を起こさないための環境を作れるようサポートします。
・医師の指示通りに内服薬を内服する
・ストレスや疲労をためない
・適切な睡眠をとる
・過度なアルコール摂取をしない
ほかにも、発作を見据えた危険物の除去や食事中・入浴中の発作への対応方法など、家族への説明事項は多岐に渡ります。
てんかん発作時の観察と対応
てんかん発作時には、発作の状況把握と適切な介入が必要です。
てんかん発作時の観察項目は以下の通りです。
・てんかん発作の発症時刻、持続時間、症状
・発症時の状況
・前兆の有無
・バイタルサイン
・てんかん発作に伴うケガの有無 など
てんかん発作は、検査のための減薬中や内服薬の調整中のときに起こりやすいといわれています。
てんかんの治療状況や前兆の有無、てんかん発作時の対応方法など、カルテや本人からの聴取で事前に把握しておくと発作時にスムーズに対応できるでしょう。
てんかん重積時の救急対応
てんかん発作の多くは、数秒〜数分間で症状が落ち着きます。
しかし、てんかん発作が5分以上続いたり、発作を何度も繰り返したりする重積発作が起こる可能性があります。
脳波異常が長く続くと脳は不可逆的な損傷を起こすため、なるべく早く発作を抑えることが大切です。
重積発作が起きた場合は、すぐに医師に報告し指示を仰ぎましょう。
事前に重積発作時の対応について、医師や患者さまと話し合っておくことも必要です。
参照:厚生労働省/てんかん対策
てんかんに対する看護を学ぶなら訪問看護もおすすめ
てんかん発作を繰り返し起こす「てんかん」の治療は、てんかん発作を起こさないことが目標です。
そのため、てんかん発作を起こさない環境づくりと発作時の適切な対応が重要であり、患者さま一人ひとりに合った生活指導が必要です。
てんかんは、発作のリスクを抱えながら自宅で生活を送る方も多い病気です。てんかんに対する看護を学びたい方は、訪問看護師としての働き方もご検討ください。
転職後検討中の方は、ぜひ『訪問看護ステーションリスタ』へお問い合わせください。