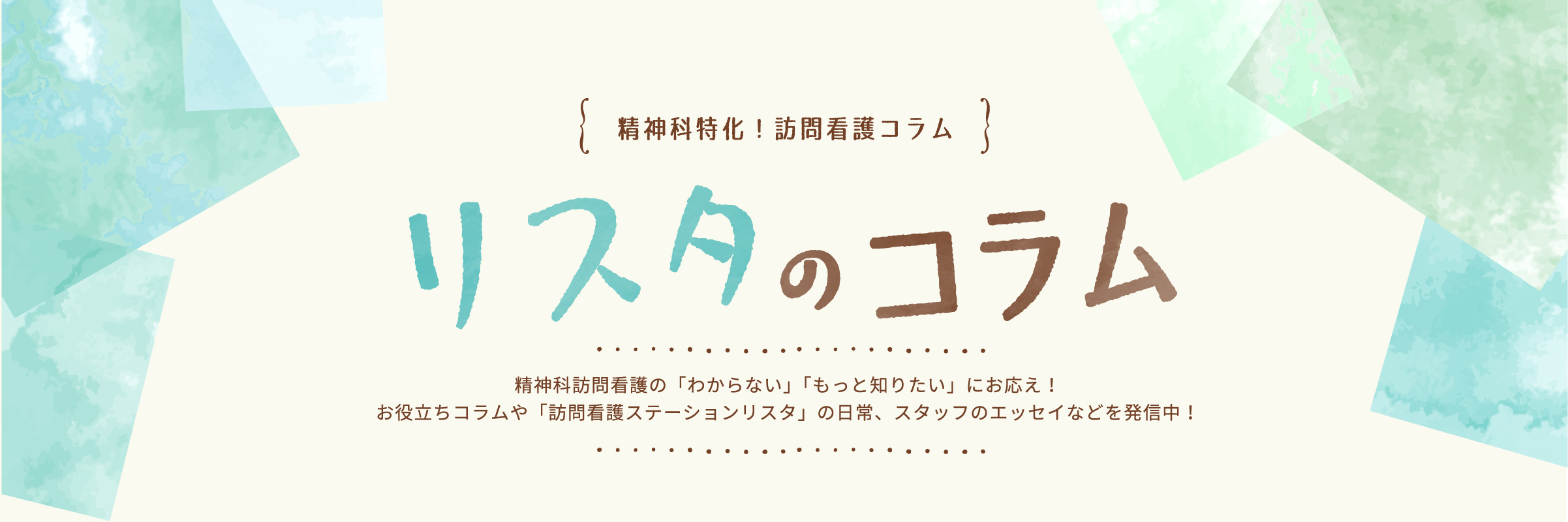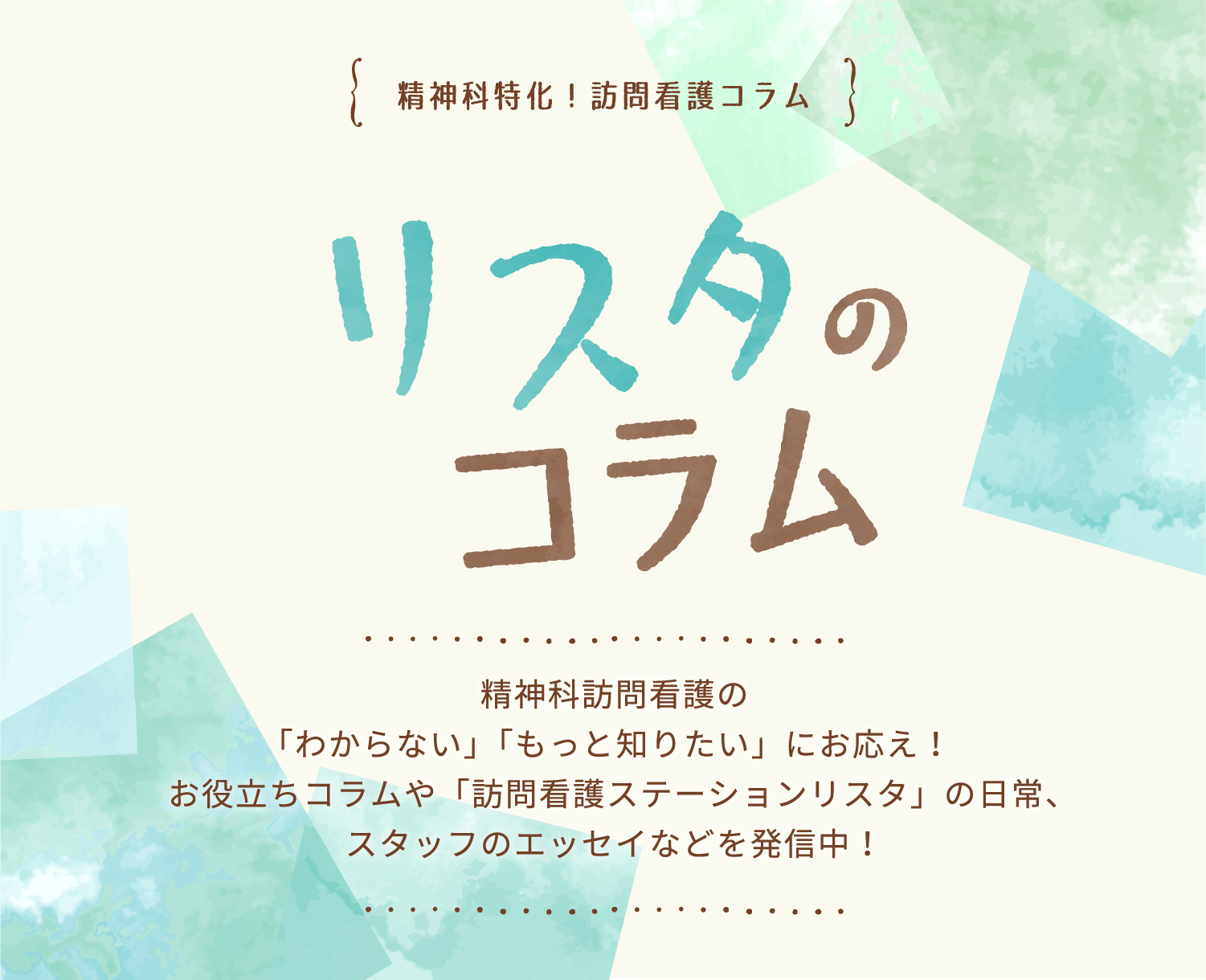被害妄想は病気なの?正しい対応と意識したいポイントを解説
2025.02.17
被害妄想がある方への看護は、対応方法に配慮する必要があります。
適切な対応のポイントを押さえ、利用者さまがすみやかに日常生活へ復帰できるようサポートしましょう。
この記事では、被害妄想を持つ方への対応のポイントを解説します。
患者さまとの関わり方に迷っている方や、スキルアップしたい方はぜひ最後までご覧ください。
「被害妄想」は病気なの?
被害妄想とは、自分が被害に遭っていると思い込んでしまう精神症状の一種です。
統合失調症や認知症など、精神疾患の症状として出現する場合があります。
被害妄想がある方は「お金を盗られた」「誰かに悪口を言われている」など、実際に受けていない被害を事実と思い込んでしまいます。
事実と妄想が入り混じった発言により、コミュニケーションや人間関係に問題が生じる場合も。
改善するには、薬物療法や精神療法による治療に加え、看護師と患者さまの信頼関係の構築が必要です。
看護の際は、距離感や応答の仕方など、対応に気をつけなければいけません。
被害妄想の人への対応で意識したい3つのポイント
ここでは、被害妄想が出現している方へ接する際のポイントをご紹介します。
特に注意すべき3つの点を見ていきましょう。
むやみに否定しない
被害妄想があるからといって、話のすべてを否定するのはよくありません。
被害妄想のある方は嘘をついているわけではなく、頭の中で起こっていることを本当だと思い込んでいるためです。
信頼関係を構築するためにも、否定ではなく傾聴にとどめるよう対応しましょう。
適切な距離感で接する
患者さまの妄想に振り回されないよう、適切な距離感を保つことも大切です。
距離感を誤ると、本人の被害妄想や態度に振り回されてしまい、冷静に対応するのが難しくなります。
感情的にならず、フラットな気持ちで看護するためにも、関わる際の距離感に気を配りましょう。
環境に配慮する
妄想を助長させるような環境やストレスから、患者さまを遠ざけることも重要なポイントです。
本人にとって好ましくない環境はストレスを与え、精神状態を不安定にさせてしまいます。
被害妄想を連想させるきっかけを与えないよう、本人の嫌がるものや人、生活環境からは遠ざけるよう配慮しましょう。
被害妄想への対応を学ぶ方法
被害妄想への対応方法は、独学や精神疾患の研修で身につけられます。
「日本精神保健看護学会」などの団体が開催している研修会では、被害妄想をはじめとする精神症状について学べます。
さらに実用的な対応を身につけたい方は、現場で直接学ぶことがおすすめです。
精神科や心療内科、訪問看護ステーションなどで働きながら、被害妄想に関する知識や、看護スキルを身につけるとよいでしょう。
被害妄想への正しい対応は訪問看護で身につけよう
被害妄想がある方へ看護を提供する場合、対応の際に気をつけるべきポイントを押さえておくことが重要です。
被害妄想が生じている患者さまの気持ちを理解し、適切な距離感で対応しましょう。
被害妄想のある方への対応は、精神科訪問看護の現場でも身につけられます。
『精神科訪問看護ステーションリスタ』では、一緒に働くスタッフを募集しています。ライフスタイルに合わせて柔軟な働き方を実現できます。
興味のある方は、ぜひこちらからお気軽にお問い合わせください。